あみぐるみって、ほぼ細編みでできているんです。
かぎ針で細編みを編むとき、実はその「糸のひっかけ方」に2種類あること、知っていましたか?
それが、
ヤーンオーバー式(糸がかぎ針の上にある状態でひっかけて編む方法)と
ヤーンアンダー式(糸がかぎ針の下にある状態でひっかけて編む方法)です。
「そんなのどっちでも良くない?」「正直、見た目変わる?」と思われるかもしれませんが、実は編み上がりに結構な差が出ます。
動画にそれぞれの編み方と見え方をまとめたので、気になる方はぜひご覧くださいね。
ちなみに、一般的にはヤーンアンダー式は「間違った細編み」とされがちです。
でも私は、あえてヤーンアンダー式をメインに使っています。
(正確には、ヤーンオーバーとアンダーを用途に応じて使い分けています。)
今回は、あみぐるみたまご修練場レベル5(わ編み)に入る前に、私の編み方の話をちょっとしておこうと思い、この記事を書きました。
私がヤーンアンダー式を選ぶ理由①
編み目が斜行しにくい
あみぐるみを編んでいると、編み目が斜めに傾いていく「斜行(しゃこう)」に悩まされること、ありませんか?
これ、実はかなりの死活問題で、編み図の設計や形の再現度に大きく影響します。
私の経験では、ヤーンアンダー式の方が、ヤーンオーバー式よりも斜行しにくいのです。
私がヤーンアンダー式を選ぶ理由②
継ぎ目が目立ちにくい
立体をわ編みで編むとき、毎段の「引き抜き編み+立ち上がり」の継ぎ目が目立ってしまう…そんなお悩み、ありませんか?
ヤーンアンダー式のふっくらした編み目を活かせば、その継ぎ目がうまく紛れて目立ちにくくなるのです。
私はこの現象を「木を隠すなら森に隠せ」戦法と呼んでいます。
つまり、「引き抜き編みをした継ぎ目部分を短くして隠す」のではなく、継ぎ目も1目に見せかけて、全体に紛れさせてしまうという方法です。
①と②の効果を比較した画像はこちらです。

私がヤーンアンダー式を選ぶ理由③
裏編みとの違和感が少ない
これは少し高度な話ですが、平面を往復編みする時、編み地の裏面(返し段)では、どうしてもヤーンアンダー式の動きに近くなるんです。
つまり、表はヤーンオーバー/裏はヤーンアンダーになると、編み目の表情がガラッと変わってしまうんです。
これ、私はすごく気になってしまうタイプで…。
なので、裏編みでも自然につながるように、ヤーンアンダー式に揃えることで統一感を出しています。

もちろん、ヤーンオーバー式も使います
ヤーンアンダー式は、目が立体的でふっくらする分、編み地がぽってりと厚みを持ちやすい特徴があります。
なので、すっきり見せたいときや繊細な印象を出したいときは、ヤーンオーバー式を選ぶこともあります。
仕上がりや使うシーンに応じて、それぞれを使い分けながら編んでいます。
これから始まる あみぐるみたまご修練場レベル5 では、「わ編み」に挑戦していきます。
その中で私自身は、主にヤーンアンダー式で編んでいく予定です。
賛否あるかもしれませんが、これもひとつの編み方として、
「occultAm式」として受け取っていただけたらうれしいです。
ここまで読んでくださり、ありがとうございました。
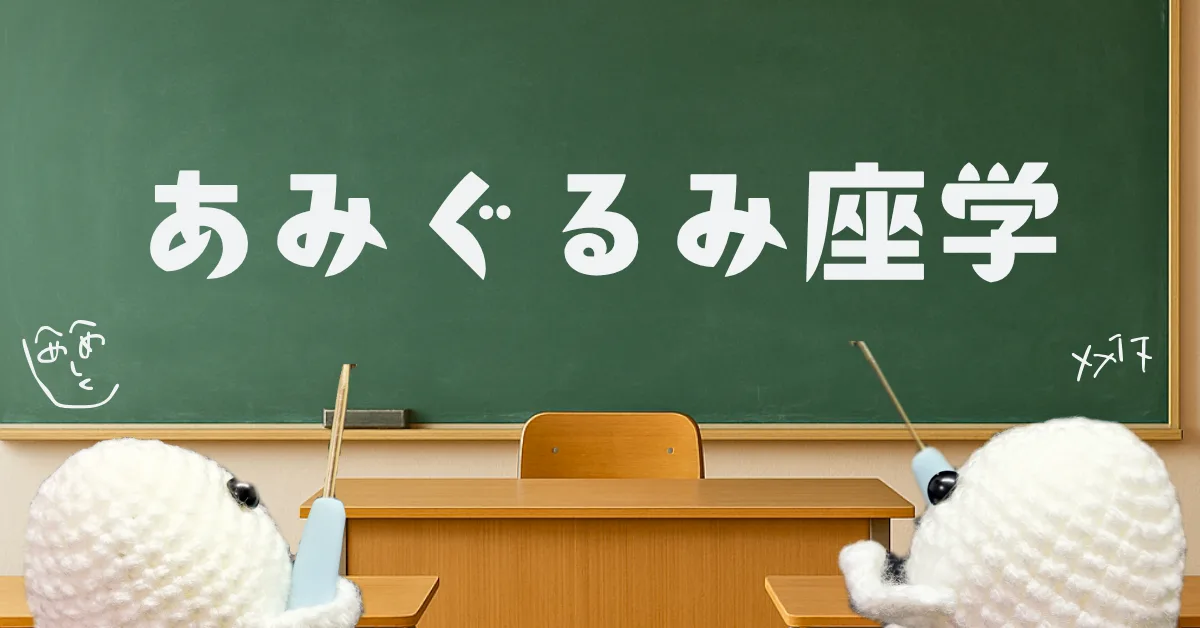
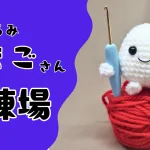
コメント